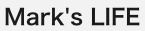一昨日、動物愛護センターへ行く途中、四国霊場51番札所の石手寺の前を通りかかった。
パッと、通りから見た瞬間「あれっ、ここ来たことあるなぁ」と思った。
そのときは、そこがお遍路八十八ケ所のお寺の一つだとは思っていなかったのだ。

石手寺の正面は、他のお寺にはない、非常に独特な雰囲気があり、一度来たら忘れられない。
僕が、まず覚えていたのが、お堂に行き着くまでの参道がアーケードの様になっていて、両側にお店が並んでいるところ。
薄暗く、まるで地下のアーケードを歩いている様にも感じる場所だ。

暗く感じる理由は、ほとんどが閉店しているということもある。
10件以上のお店があるが、営業していたのは3店舗程度だった。
それも、きっと誰も買わないだろうと思われる様な商品が並び、さらには、僕が少し気になって見た小型のほうきがあったのだが、値段を見てびっくり1,200円と書かれていた。
間違いではないか?
と、思って他の商品も見たが、どうやら間違いではなく、どの商品も、とんでもない価格が書かれていた。
「こりゃ、全盛期の価格から変わっていないんだろうな」
前は売れたのだから、売れるに違いない!そう思い込んで、きっと何十年も経ったのだろう。そんなことを思わせる様な、商品構成と値付けだった。

そんな、古びたアーケードを抜けると、お寺のメイン、お堂と塔が見えてくる。
アーケードと釈迦の一生を描いたたくさんの彫刻以外は、あまり覚えていなかったのだが、このお寺、非常に楽しめる。

お寺のアミューズメント施設といってもいいかもしれないほどなのだ。
きっと、お遍路で来たときにも通ったと思うが、洞窟が2箇所あり、1つは、薄明かりがついた長い洞窟。
こちらは、天然の岩盤をくり抜いて作られており、きっと、大昔に作られたのだろうと感じる洞窟だ。


もう一つは、洞窟ではなく、何らかの意図を持って作られた、真っ暗な細い道を歩いて行くもの。
ここに入った瞬間に、盲目の人たちが運営している「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」を思い出した。
目がまったく見えない世界。
目の見える僕にとっては、体験するまで、そんな世界があることは、頭では知ってはいるが、実際には理解はしたことはなかった。
街灯がない様な場所で、月明かりも、星の輝きもない時、ほぼ、真っ暗で何も見えないという経験はするものの、手元には明るさを補うためのものが何かしらあり、すぐに明かりを点けてしまう。
結局は、真っ暗な中で行動しなければならないなどという経験はすることはない。
初めてダイアログ・イン・ザ・ダークへ行った時、本当の暗闇を体験した。
きっと、生まれる前以来の経験だっただろう。
その時、いかに視力に頼って日々を生きているかを実感した。
そして、最初は見えないことへの恐怖があるが、慣れてくると、たまには見えないのもいいとも思えてくる。
その分、聴覚や触覚の感覚が際立ってくるのである。
さて、石手寺の洞窟は、そんな真っ暗な回廊を歩いていく。
中は、曲がりくねっており、さらに階段もある。
本当に真っ暗闇で、どんなに目を凝らそうが何も見えない。
そんな時は、目をつぶって、他の感覚を頼りにした方が賢明なのだ。
しばらく歩いていると、行き止まりになってしまった。
「あれっ?どっかで間違えたかな?」そう思い一度戻って、違う道を探したのだが、結局、入り口に出た。
もう一度、出口に出られる様に暗闇に入っていった。
しかし、一度「道を間違えた」という経験をしたことによって恐怖が芽生えてきた。
「もしかしたら、出口にたどり着けないのではないか?」
「もしかしたら、入り口にも戻れないかもしれない」
「そうなったら、どうやって助けを呼べばいいのだろう?」
意外にも長い真っ暗な道のりなため不安に思えてきたのだ。
今考えてみると、本当にまずければ、iPhoneのライトを点灯させて進んでいけば良いだけのことなのだが、その時は、なぜか、まったくそうした思考にならななかった。
目をつぶって、道の両側の壁を触りながら触覚だけを頼りに進んでいった。
すると、何となく、ぼんやりとまぶたの外から光が来ているような感覚になったので、目を開けてみると、無事に出口にたどり着いていた。
何だか、ダイアログ以来?いや、きっとお遍路以来なんだろうけど、暗闇というものを、時々体験するというのは実にいいものである。
暗闇だけではない、今、あるものが「無い」という経験というのは、新しい発見をさせてくれるものだ。
往々にして、現状の「無い」を見て、手に入れようと「ある」を追いかけていくというのが、人生の大半だ。
しかし、物質だけではなく、何かを手放してみるというのは実に新鮮だし、「無い」を意図的に経験するのは、なかなか面白いものである。
そんなこんなで、Amusement Templeを存分に楽しんでみた。